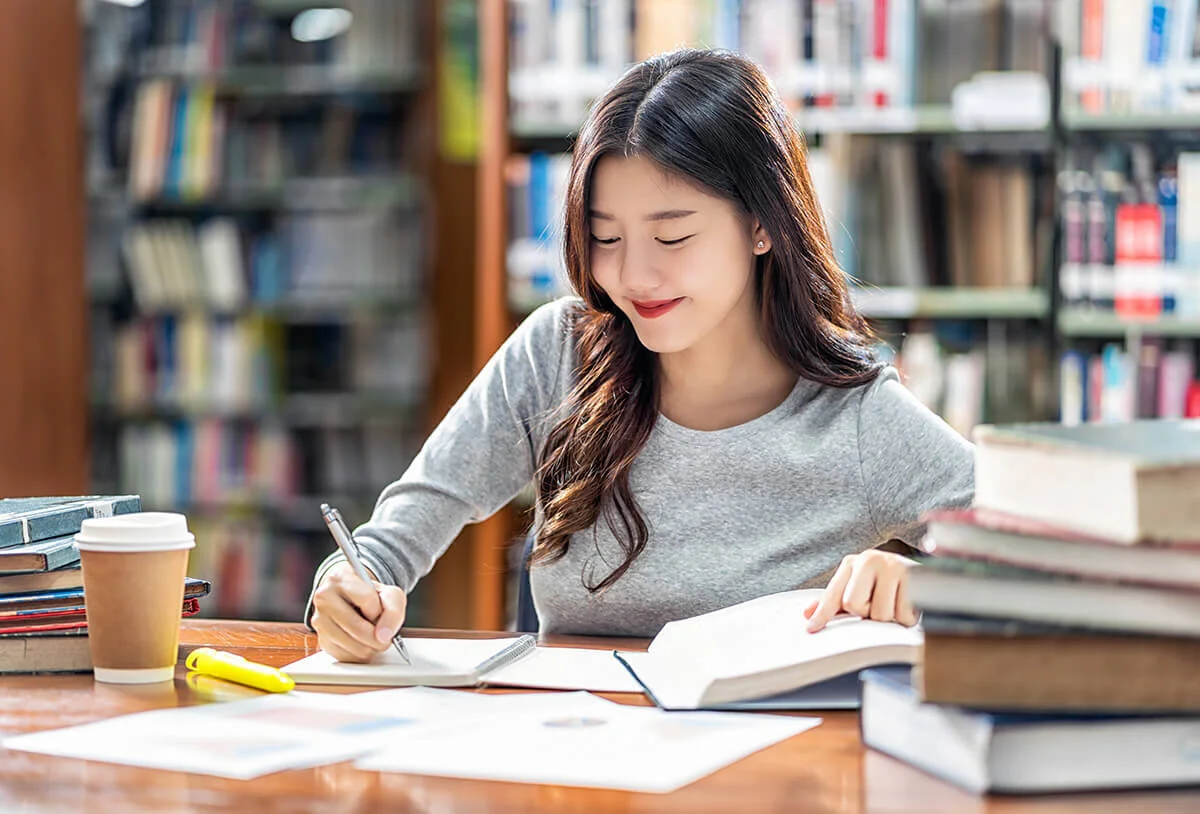ドイツ語の試験レベル 独検 5級~ 1級【独日翻訳者で必要とされている試験】🇩🇪 ドイツ語技能検定試験(Diplom Deutsch in Japan)
独検は翻訳を目指すかたにおすすめ!
最初に、独検はドイツ語を日本語に訳す翻訳家を目指したいかたにおすすめな試験です。というのも、独検の試験内容はレベルが上がるほど日本語に訳すのがとても難しくなるからです。ドイツに住みたい、ドイツで働きたい、という目標を持っている場合はドイツ国内の試験を受けるほうが役立つと思います。
逆に日本国内の就職では、ドイツ国内の試験よりも独検のほうが有利だった、と私の友達が言っていました。これはドイツ国内の試験は日本国内ではマイナーで知らない面接官が多く、独検は名前からしてもなんだか凄そうなイメージがあるからだと思います。なので、日本で就職するために独検を取るのは全然アリです。
こんにちはマキシーです!今回は、独検のレベルについてご紹介していきます。
独検は翻訳を目指すかたにおすすめ!
最初に、独検はドイツ語を日本語に訳す翻訳家を目指したいかたにおすすめな試験です。というのも、独検の試験内容はレベルが上がるほど日本語に訳すのがとても難しくなるからです。ドイツに住みたい、ドイツで働きたい、という目標を持っている場合はドイツ国内の試験を受けるほうが役立つと思います。
逆に日本国内の就職では、ドイツ国内の試験よりも独検のほうが有利だった、と私の友達が言っていました。これはドイツ国内の試験は日本国内ではマイナーで知らない面接官が多く、独検は名前からしてもなんだか凄そうなイメージがあるからだと思います。なので、日本で就職するために独検を取るのは全然アリです。
独検の種類と難易度
独検の種類と難易度は以下のようになっています。2級あたりから難しくなりますが、準1級からは本当に難しいです···。
独検1級:鬼難しい
独検準1級:激難しい
独検2級:難しい
独検3級:普通
独検4級:簡単
独検5級:とても簡単
まず、自分がどのくらいの実力があるのかを知りたい場合は、独検の公式サイトに模擬試験が公開されているので、それをダウンロードしてチャレンジしてみるのがおすすめです。
また、冒頭で独検は翻訳家を目指しているかたにおすすめとご紹介しましたが、2級あたりから翻訳に関する内容が増えてくるので、翻訳家になりたいなら最低でも2級以上の試験に合格することを目指したいところです。
独検5級
独検5級は一番シンプルで、一部のドイツ語に関する試験です。試験で使われる単語の数は550個、90分の授業を20回くらい受ければ合格できると思います。
独検4級
独検4級は試験の中で使われる単語が約1,000個くらい、90分の授業を40回くらい受ければ合格できると言われています。4級に受かればドイツ語の簡単な日常会話は理解できるようになります。
独検3級
独検3級は単語の数が約2,000個くらい、90分の授業を80回くらい受ければ合格できるレベルです。ドイツ語のコラムや短文のリスニングなど、このあたりから徐々に試験の難易度が高くなってきます。
独検2級
独検2級は単語の数が約3,000個くらい、90分の授業を120回くらい受ける必要があると言われています。本格的にドイツ語をやろうと思ったら、独検2級は1つの目標となってきます。
独検準1級
独検準1級は単語の数が約5,000個、このレベルはとても難しいです。ドイツ国内で不自由のない生活を送れるくらいのドイツ語力がなければ合格は難しいと言われています。新聞など複雑な記事も出てくるので、完全に上級者向けの試験となっています。
独検1級
独検1級はもっとも難しいレベルです。私も受けてみましたが、日本語に翻訳するのが本当に難しかったです。しかし、独検1級を取ることができれば、自慢できるどころか翻訳家としても本格的に仕事をすることができますし、努力次第で合格できるかもしれないというかたはぜひチャレンジしてみてほしいと思います。
独検はGoetheにたとえるとどのくらいのレベル?
独検のレベルをドイツ国内のGoetheにたとえると、どのくらいのレベルなのかも参考程度にご紹介します。
独検1級:C1~2
独検準1級:B2
独検2級:B1
独検3級:A2
独検4級:A1~2
独検5級:A1
大体、上記のようなレベルと言われていて、独検3級に受かるならGoetheのA2相当といった感じですね。
独検の合格率はどのくらい
最後に独検の合格率についても参考としてご紹介します。
独検1級:20%が合格
独検準1級:29%が合格
独検2級:65%が合格
独検3級:58%が合格
独検4級:76%が合格
独検5級:96%が合格
※2016年のデータ
難易度が高くなるほど合格率も低くなる傾向があり、独検1級は一番合格が難しいです。もし、就職の際に面接官に独検をアピールしたいなら、1級を持っているなら20%しか合格できないことを強調してみるといいかもしれませんね。

ドイツ情報のメルマガ
20ヶ国語話せる人に聞いてみた❗️ドイツ語と日本語の違いも教えてもらった
Maxie「こんにちは、自己紹介をお願いします!」
Steve「こんにちは、カナダのバンクーバーに住んでいるスティーブ=カークと申します。言葉が非常に大好きで、息子と一緒に「 www.lingq.com 」という言葉を学ぶサイトを運営しています」
Maxie「今日はスティーブさんにドイツ語を勉強するようになったきっかけについてお聞きしたいと思います」
Steve「私は5歳の時に家族でカナダに移住しましたが、両親はチェコ出身のドイツ人です。ユダヤ人の多くはドイツ語とチェコ語が話せるため、両親はドイツ語とチェコ語で会話していました。ただ僕と兄はカナダに住んでいたため、英語で話すように言われていたので、ドイツ語を話すことはなかったのですが、少しはドイツ語にもなじみがありました。19歳のときに、ドイツで建築労働者として2週間ほど仕事をすることがあったのですが、その時には私の中途半端なドイツ語も役に立ちましたね。(笑)
そして1987年、自分の木材関係の会社を立ち上げました。ヨーロッパや日本ともかかわりを持つことになり、日本にも9年ほど住んでいたことがあります。そして会社を立ち上げたころ、ドイツ語を本格的に勉強しようと思い、本屋さんでドイツ語のテキストやカセットテープなどの教材を購入し、独学で勉強していました。その当時のテキストは、語彙集が充実していたので、テキストの傍ら辞書を開くような手間も必要なく、集中して勉強ができました。その後ドイツで仕事をする機会があった時には、アウトバーンの大渋滞に巻き込まれた時などを利用して、ドイツ人のエージェントやスタッフとたくさん会話して少しずつドイツ語をマスターしていきました。」
ドイツ語と日本語の違い
Maxie「ドイツ語と日本語の違いってなんですか?」
Steve「英語を母語としてドイツ語を学んでいる立場から言うと、ドイツ語はゲルマン系の言葉なので、ラテン語や英語とも文法や語彙の面で共通点が多く勉強しやすい言語です。一方の日本語は、英語などとの共通点が少ないうえ、漢字·ひらがな·カタカナと表記も複雑で難しい。私は日本語を勉強する前、中国語を学んでいたので、漢字は大体わかります。だけど、ひらがなやカタカナが難しく苦労しました。
ただし、日本語は語彙や文法が難しいけれど、柔軟性があって、特に外国人はあまりにもラフな言葉でなければ敬語を使わなくてもとがめられることはないです。ドイツ語は細かい決まりが多くて、ロジックをわかっていても間違う可能性が高い傾向にあります。」
ドイツの発音が難しい?!
Maxie「日本人によく『ドイツの発音が難しい』って言われますが、発音はどんなふうに勉強したらいいですか」
Steve「ドイツ語が難しいというのは、何に比べて難しいのだろう?ロシア語に比べて難しいですか?アラビア語や中国語のピンインに比べて難しいのでしょうか?どの国の言葉でもそうだけど、発音を真似するというのは時間がかかります。そしてたくさん聞かなければいけない、聞き取れないと発音ができないですね。さらに発音が難しいというのは人間の心理に影響しています。日本人がドイツ語をネイティブのように発音しようと思ったとき、『この発音はおかしくないか?下手なんじゃないか』と不安になるかもしれない。でも勇気をもってたくさんのドイツ語を聞いて、聞いたとおりに話すしかドイツ語をマスターする方法はないです」
ドイツの好きな単語
Maxie「ドイツの好きな単語はありますか」
Steve「正直に言ってドイツの言葉全部好きですよ。どの国の言葉でも、正しく発音しようと思ったらその言葉を好きにならないといけないと思います。日本語でもドイツ語でも優雅なところを感じて吸収しないといけないです。ある人にとってのドイツ語は文章が長くて、複雑でややこしいものに感じるかもしれません。だけどそれがドイツ語の魅力でもあるわけです。日本語もフランス語のようにロジカルに話す言語でもない。回りくどい言い回しもある。でもそれが日本語のエレガンスでもある、それを好きにならないと日本語が話せない。だからどの単語が好きというのではなく、すべて好きです。それはロシア語でもアラビア語でも同じだと思います。」
ドイツ人とかかわって驚いたこと
Maxie「ドイツ人とかかわって驚いたことはなんですか」
Steve「驚いたこと…は、ないですね。ただドイツ人はすごくまじめだというイメージがありました。でも実際にドイツで、ドイツ人のなかで働いてみると、明るくて陽気でした。ドイツの船にのって仕事をしている人で酔っぱらっていた人のほとんどがドイツ人だったと記憶しています。ドイツ人は基本的に外国の人にも優しい国民性を持っていると思いますよ。
ただ、そんな陽気で楽しいドイツ人にも厳しい一面もあります。たとえば日本で外国人がたどたどしい日本語で話しかけてきた場合、日本人なら最後まで聞いてあげた後、日本語で返事をします。だけど、ドイツ人は忙しいから(笑)最後まで聞かずに英語で答えます。ドイツ人にはこういった厳しい一面があるので、やはりドイツ語はしっかりと勉強する必要があります。(笑)」
これからドイツ語を勉強したい人に向けての応援メッセージ
Maxie「これからドイツ語を勉強したい人に向けての応援メッセージお願いします!」
Steve「ドイツという国はヨーロッパにおいて非常に大切な国です。西ヨーロッパでも東ヨーロッパでもそれは同じ。歴史を調べればフランスでもともとゲルマン民族でしたし、東ヨーロッパでも、バルト三国などではドイツの影響が非常に大きいです。それこそ中央ヨーロッパにおいて哲学、化学、音楽、芸術、すべての面で影響力の大きい国です。私が世界各国の言葉を知りたいのは、世界のことが知りたいからです。だから、ヨーロッパを知りたいならドイツやドイツ語をよく知らないといけません。ドイツ語を難しいと思わずに楽しみながら勉強してください」

ドイツ情報のメルマガ
電子辞書 ドイツ語 買うかどうかについて (カシオ 電子辞書 エクスワード ドイツ語モデル XD-N7100)
結論から言いますと、ドイツ留学に向けて電子辞書があれば便利なのは間違いありませんが、スマホを持てるのであればスマホの辞書アプリで代用できるので、1つのポイントになるのはスマホです。
私が日本に来たのは約10年前くらい、高校2年生のときでした。当時は、日本語をまったく話せない状態で、スマホも持っていませんでしたし、電子辞書にはかなり救われました。今でもその時に使っていた電子辞書を愛用していて、かれこれ10年ほど経つのに故障もせずにまだまだ現役です。
その経験から感想を述べると、基本的にスマホで代用できますが、電子辞書のほうが辞書アプリよりも調べるスピードが早いメリットもあるので、実用性も加味しながら検討してみるのがいいと思います。どちらにすべきか迷うのであれば、電子辞書を買って後悔することはない、これだけは断言できます。
結論から言いますと、ドイツ留学に向けて電子辞書があれば便利なのは間違いありませんが、スマホを持てるのであればスマホの辞書アプリで代用できるので、1つのポイントになるのはスマホです。
私が日本に来たのは約10年前くらい、高校2年生のときでした。当時は、日本語をまったく話せない状態で、スマホも持っていませんでしたし、電子辞書にはかなり救われました。今でもその時に使っていた電子辞書を愛用していて、かれこれ10年ほど経つのに故障もせずにまだまだ現役です。
その経験から感想を述べると、基本的にスマホで代用できますが、電子辞書のほうが辞書アプリよりも調べるスピードが早いメリットもあるので、実用性も加味しながら検討してみるのがいいと思います。どちらにすべきか迷うのであれば、電子辞書を買って後悔することはない、これだけは断言できます。
電子辞書のメリットとデメリット
電子辞書にはどのようなメリットやデメリットがあるのか、まずはこれについて見ていきましょう。
【電子辞書のメリット】操作性に優れていて使いやすい
電子辞書はキーボードが設置されているタイプがスタンダードで、充電すればずっと使うことができます。
キーボードがあるので調べるのが早い
画面もキーボードもほどよい大きさで使いやすい
サブスクリプション契約がない(月額契約のこと)
スマホよりもサイズが大きいため、快適な操作性かつ調べるスピードが早いことが電子辞書のメリットです。
【電子辞書のデメリット】落としたら壊れてしまう
電子辞書を使う上で気を付けておきたいのが、落としたら故障してしまうことです。当たり前のことなのですが、電子辞書を落として壊れてしまった経験のある留学生は割と多いと思います。私も何度も落としたことがありますから···。
落としたら壊れてしまう
それなりに値段が高い
学校によっては電子辞書がNGなケースも
このデメリットを払拭するためにも、もし電子辞書を買うのであれば必ずカバーケースもセットで購入してください。これが有るのと無いのとでは大違いです。
スマホのメリットとデメリット
続いて、スマホのメリットとデメリットについて見ていきましょう。
【スマホのメリット】辞書以外にもネットやSNSなど機能性が凄い
スマホのメリットについてはみなさんご存知のとおりです。スマホがあれば大抵の問題は解決できますよね。
辞書アプリが豊富
ネットやSNSなど機能性に優れている
スマホ1台で大抵の問題を解決できる
辞書アプリについてもいろんな種類のアプリがリリースされていて、そのほとんどを無料で利用することができます。
【スマホのデメリット】携帯がダメな学校がある
一方、スマホのデメリットになるのは、以下のような内容です。
契約しなければならない
サブスクリプション契約でずっと料金がかかる
学校によってはダメなケースも
そもそも、スマホを使うためには契約しなければならないため、家庭によってスマホを持てるかどうかは大きく変わってきます。また、学校によってはスマホがNGなところがあるので、その場合は電子辞書を活用したいですね。
余談ですが、スマホがNGな学校があるように電子辞書がNGな学校ってあるんでしょうか。もし、そういう学校があるなら、今のハイテクな機械が日常に溢れている時代に合わないですよね。スマホNGはまだわかりますが、電子辞書NGの学校があるならダメな理由がとても気になります。
電子辞書はいくらくらい?
電子辞書は非常に多くの種類が販売されていますが、相場は約15,000円~50,000円とピンキリです。
ドイツ語の習得におすすめの電子辞書は?
学習から実務まで対応。実践的なドイツ語をしっかり学びたい方に。
電子辞書は英語とドイツ語がセットになっているタイプや英語電子辞書に多言語を追加するタイプなどさまざまですが、おおよその相場は上記と変わりません。また、このお値段で国語系の学習機能やTOEICなどの試験対策ができるなど、機能性が豊富でもあります。
ドイツ語をしっかり学びたい方に、カシオ 電子辞書 エクスワード ドイツ語モデル XD-Z7100 100コンテンツをおすすめします。
ドイツ語のコンテンツが収録されています。大規模コーパスを活用したアクセス独和辞典ほか役立つドイツ語コンテンツがいっぱいあります。
・小学館 独和大辞典 第2版(収録数:約160,000語)
・アクセス独和辞典 第3版(収録数:約76,000語)[ネイティブ音声収録]
・アクセス和独辞典(収録数:約56,000語)
・オックスフォード ドイツ語辞典(収録数:約320,000語)
・DUDEN独独辞典第6版 (収録数:見出し語・成句約150,000語)
・口が覚えるドイツ語(収録数:585例文)[ネイティブ音声収録]
・文法中心 ゼロから始めるドイツ語(収録数:全22課)[ネイティブ音声収録]
・ひとり歩きの会話集 ドイツ語(収録数:約2,000例文)[ネイティブ音声収録]
・Dr.PASSPORT日本語→ドイツ語版(収録数:約350項目)[ネイティブ音声収録]
・Trouble Passport日本語→ドイツ語版(収録数:約630項目)[ネイティブ音声収録]
このような関連機能があることもスマホの翻訳アプリにはない電子辞書ならではのメリットだといえるでしょう。

ドイツ情報のメルマガ
ドイツの大学は無料だ!!ボン大学の生活費&家探しについて (ドイツ留学について)
ドイツ留学を考えたとき、いくらお金がかかるのか気になりますよね。今回は、ドイツ留学の学費や生活費などについてご紹介していきますので、ドイツ留学を検討しているかたはぜひ参考にしてみてください。
こんにちはマキシーです!ドイツ留学を考えたとき、いくらお金がかかるのか気になりますよね。今回は、ドイツ留学の学費や生活費などについてご紹介していきますので、ドイツ留学を検討しているかたはぜひ参考にしてみてください。
ドイツの国立大学は無料!
まず、ドイツの大学の費用からご紹介しますが、私立大学は有料なものの、なんと国立大学は無料です!
ドイツの国立大学は基本的に無料となっていて、共済費が約150~350ユーロ(約19,500~45,500円)ほどかかる程度です。共済費というのは、学生の自治会費や登録費などの事務管理費のことで、交通機関が無料になるSemester ticketの費用も含まれています。
2017年にバーデン·ビュルテンベルク州でEU以外からの留学生の授業料が変更されて1500ユーロ(約195,000円)ほどかかるなど、国立大学でも州によって状況は異なります。しかし、原則としてドイツの国立大学の学費は無料という認識でOKで、無料で通える国立大学を探せば必ず何かは見つかるほどです。
ちなみにドイツの国立学校は大学だけではなく、原則として小中高とすべて無料で国籍も関係ありません。
※ユーロの円換算はすべて1ユーロ=130円で計算。
ドイツ留学の生活費
もし、ドイツの国立大学に留学するなら学費は無料なので、生活費さえしっかり確保すれば学生生活を送ることができます。
ドイツの生活費をまとめてみると、以下のような金額です。
Wohnen(家):290~563ユーロ(約37,700~73,190円)
Essen(食事):140~213ユーロ(約18,200~27,690円)
Fahrkosten(旅費 & 交通費):―(Semester ticketを使えば無料)
Kleidung(服):32~59ユーロ(約4,160~7,670円)
Telefon & Internet(電話とインターネット):25~39ユーロ(約3,250~5,070円)
Lernmittel(学習支援):19~27ユーロ(約2,470~3,510円)
Krankenkersichervng(健康保険):0~190ユーロ(約0~24,700円)
Freizeit(遊ぶお金):47~89ユーロ(約6,110~11,570円)
Gebuhren(何かの支払い):12~187ユーロ(約1,560~24,310円)
Kosten(費用合計):646~1,507ユーロ(約83,980~195,910円)
合計すると、1ヶ月に日本円で約83,980~195,910円くらいです。食事や家賃で合計額は大きく変わりますが、贅沢な暮らしをしなければ80,000~100,000円ほどあれば十分に生活できます。
Wohnen(家)
ドイツ留学では、生活費でもっともお金がかかるのは家賃です。住む場所によっても家賃相場は大きく異なりますが、290~563ユーロ(約37,700~73,190円)くらいです。大体、300~500ユーロはかかると思っておいてください。学生寮があれば安く済ませられるので、それによっても大きな違いがでます。
Essen(食事)
食事は1日3食がスタンダード、毎日食べるだけに食費も生活費の大きな負担です。なるべく外食を控えて料理を作るようにすれば、140~213ユーロ(約18,200~27,690円)くらいに抑えられると思います。ドイツは日本に比べて物価が安く、とくにスーパーへ行けば安く食料品を調達できるので、工夫をすればしっかり食費を抑えられます。
Fahrkosten(旅費 & 交通費)
ドイツに留学していろんな観光名所を巡りたいなら旅費や交通費がかかりますが、普通に生活するだけならSemester ticketを使えば交通費は無料です。これは大学から発行されるカードのことで、その大学がある州の交通機関を無料で利用できるという学生の特権ともいえるサービスです。
Kleidung(服)
服の費用は32~59ユーロ(約4,160~7,670円)くらいです。私の印象では、日本女性にとってドイツの衣類はサイズが大きいため、ドイツ留学をして服をたくさん買うことは少ないような気がしなくもありません。私の知り合いの日本人の中にはドイツの服が好きじゃない人もいましたし、人によって服にかかる費用は個人差が大きいと思います。
Telefon & Internet(電話とインターネット)
携帯とネット環境は25~39ユーロ(約3,250~5,070円)くらいです。日本に比べるとドイツのほうが料金は安いです。また、学生寮に入ればインターネットは無料で使うことができます。
Lernmittel(学習支援)
学生生活ではノートをコピーするなど、いろいろとお金がかかりますよね。そのような学習に関する出費は19~27ユーロ(約2,470~3,510円)くらいです。
Krankenkersichervng(健康保険)
健康保険は0~190ユーロ(約0~24,700円)くらいです。ドイツ留学は絶対に医療保険に加入しなければなりませんが、日本からドイツへ行く場合は保険の選択肢がとても多く、加入先によってもピンキリです。一般的には旅行保険に加入するケースが多いと思います。
Freizeit(遊ぶお金)
ドイツ留学で遊ぶお金は47~89ユーロ(約6,110~11,570円)くらいでしょうか。これもピンキリなので、出費を抑えるなら0円も可能ですね。
Gebühren(何かの支払い)
学生生活では、物を買うなど何かしらの支払いが出ることがあると思いますが、12~187ユーロ(約1,560~24,310円)、少し多めに想定するなら200ユーロくらいを見ておくと安心できそうです。
Kosten(費用合計)
ドイツ留学の生活費を合計すると、646~1,507ユーロ(約83,980~195,910円)くらいを考えておきたいですね。ドイツのどのような地域の大学へ留学するのかで費用は変わってくるので、ここが大きなポイントになると思います。ミュンヘンやベルリンなど都内になるほど物価は高くなりますし、田舎になるほど安くなります。とくに東ドイツは圧倒的に安いので、参考にしてみてください。
ボン大学の費用
私はボン大学の出身なので、ボン大学についても軽くご紹介しておきたいと思います。
Wohnheim(寮):203~648ユーロ(約26,390~84,240円)
W6(ルームシェア):250~500ユーロ(約32,500~65,000円)
Wohnung(1人暮らし):400~800ユーロ(約52,000~104,000円)
Fahrkosten(Semester代):6ヶ月で292.16ユーロ(約37,980円)
ボン大学の寮は200~650ユーロくらいで、結婚している学生が入れる広い寮になると650ユーロほどの高い家賃がかかりますが、安い寮なら200ユーロくらいです。また、人がたくさんいるのが嫌で1人暮らしを考えるなら400~800ユーロほどは見ておきたいですね。
あと、半年に1回はボン大学にSemester代を支払う必要があり、今だと292.16ユーロ(約37,980円)くらいです。この金額にはSemester ticketも含まれていて、ボンの電車やバスが無料になります。ボン大学のあるノルトライン=ヴェストファーレン州の交通機関も無料になるので、交通費がかからず安い生活を送ることができます。私の学生生活を思い返すと、当時の生活費では日本で生活できなかったかもしれない、それほどにドイツは安いです。

ドイツ情報のメルマガ
ドイツ語で日常会話ができるまでどのぐらい時間かかった?
ドイツ語を始めたのが大学1年の4月からで、その年の8月に、ボンに4~5週間留学したんだけど、その時には「ちょっとドイツ語力が上がったな」と思った。スーパーでの買い物やバスでの移動の際に使ったり、クラブなんかで遊ぶときに現地の友達としゃべったりして日常会話でも使えるようになったのが大きかったと思う。だからトータルで5か月くらいかな」
「日本で勉強してた時にはどのくらいのレベルまで力がついた?」
「大学で週に4回のクラスを4~7月まで受けていたから、基本的には話せたと思う。その時のクラスがA2という下から2番目のクラスで、A2は日常会話には困らないレベルは習得できるよね?ちゃんと自分の行きたいところへのバスの切符を買ったり、タクシーのドライバーに伝えることができるレベルになってから留学した」
◆ドイツ語で日常会話ができるまでどのぐらい時間かかった?
Maxie「まず、どうしてドイツ語を勉強しようと思った?」
Himawari「もともとはドイツ語を勉強したいと思ったというよりは、デンマークに留学したかったんだよね。だから大学の第二外国語を選ぶとき、デンマーク語に近くて、しかも週4回授業があるドイツ語を選んだ。勉強するからにはドイツ語をちゃんと喋れるようになりたくてボンやミュンヘンに留学もしたし」
Maxie「よくネットの広告なんかで『1週間で外国語をしゃべれるようになる!』っていうプログラムがあるけど、ひまちゃんは、自分で日常会話ができたりとか友達ができたりとか「ある程度しゃべれるようになった」と思うまでどれくらいかかった?
Himawari「ドイツ語を始めたのが大学1年の4月からで、その年の8月に、ボンに4~5週間留学したんだけど、その時には「ちょっとドイツ語力が上がったな」と思った。スーパーでの買い物やバスでの移動の際に使ったり、クラブなんかで遊ぶときに現地の友達としゃべったりして日常会話でも使えるようになったのが大きかったと思う。だからトータルで5か月くらいかな」
Maxie「日本で勉強してた時にはどのくらいのレベルまで力がついた?」
Himawari「大学で週に4回のクラスを4~7月まで受けていたから、基本的には話せたと思う。その時のクラスがA2という下から2番目のクラスで、A2は日常会話には困らないレベルは習得できるよね?ちゃんと自分の行きたいところへのバスの切符を買ったり、タクシーのドライバーに伝えることができるレベルになってから留学した」
◆ドイツは勉強してから行くべき?現地で勉強を頑張るべき?
Maxie「ドイツ語を少しでも勉強してからドイツに行くべきと思う?それともドイツ語が全く分からなくてもドイツに行ってから勉強するほうがいい?」
Himawari「少しは勉強していった方がいいかな。少しでも勉強して、知ってる単語や知ってる言い回しがあれば、ドイツの人に伝えることもできる。そして、それに対するドイツの人の返しをきいて「ああ、こう言う使い方をするんだ」というような勉強の仕方ができるから。ドイツ語を本当に勉強したいならそこは大事なポイントかもしれない。ドイツは、ドイツ語で話しかけて、ドイツ語でコミュニケーションをとりたいって考えてる人にはドイツ語で返してくれる人が多いような気がする」
Maxie「語学のクラスはTOEFLやTOEICのスコアによってレベル分けされるのかな。よく言われるのが、日本人は、筆記の成績がいいけど、話せないから筆記テストでレベルが高いクラスに入っても、全然会話ができなくて違うクラスになることもあるって」
Himawari「あぁ、そうね。ドイツ語は文法がすごく難しいじゃない。日本人はかっちり勉強しすぎて発音がついていかないとか言い回しがついていかないとかあるよね」
Maxie「私が思うのは、文法を勉強しすぎてドイツ語についていけなくなる人が多いような気がする。文法を学ぶだけでドイツ語をあきらめるリスクが高いのはもったいないと思う」
◆ドイツ語を勉強するのにおすすめの方法や取っておきたい資格はある?
Maxie「ドイツ語を勉強するにあたって何かおすすめの教科書ってある?」
Himawari「私はドイツ語の授業で使っていた教科書と、それにプラスしてミュンヘンやボンに行ったときに、ドイツ語で書かれた日本の漫画を買って勉強してた。漫画の中身はすべてドイツ語だけど、自分が知ってる漫画だと、内容も頭に入ってくるし日本語のバージョンを知ってるから「あ、それドイツ語で言うとこうなるんだ」という発見があって、実生活でも使いやすいよね。こういう学び方は楽しいなと思う」
Maxie「楽しく勉強できるのがいいよね」
Himawari「あとは、私は耳から言語を覚えていくタイプだから、ハリーポッターのドイツ語版も見た。ドイツ語が分からないときは、英語の字幕を付けて観ると、ドイツ語が耳から入ってくるし、映画も面白いと思ってる内容だから最後まで観ることができた。何度も見ているうちに徐々にわかるようになってくるよ」
Maxie「話すのはどうやって勉強した?」
Himawari「大学で週4回の授業のうち2人がドイツ人の先生だったから、先生と話してみようとか。その先生の一人が、利用する駅が同じだったから、見つけると「よぉ」って感じで話しかけてた」
Maxie「書くのはどう?」
Himawari「書くのは、テストで書いていたりとか、ドイツ研究のゼミに入っていたので、プレゼンなんかはドイツ語で書く必要があったから、いっぱい書いてたよ。今私は、ドイツ系の企業に勤めていて、メールなんかは英語とドイツ語の両方で来るから、ドイツ語の方を読んで覚えて、自分なりのキャッチアップをしてる」
Maxie「ドイツ語に関して学生時代にとって良かった資格とか「ドイツ語がほんとにできるよ!」ってアピールできる資格とかあれば教えて?」
Himawari「日本国内で働くのなら、ドイツ語検定を取っておくといいと思う。ただ、海外や外資系の会社で働くのであれば〇〇や△△の資格の方が通用するかなと思う」
◆ドイツ語は楽しくてパーフェクトな言語!
Maxie「最後にこれからドイツ語を勉強したいという人に向けて一言!」
Himawari「ドイツ語はすごく楽しい言語だと思う。ドイツは、ミュンヘンを1歩出ると言葉が全く違うから、そういった方言を吸収していくのも楽しい。その土地ごとに言葉が違って、別の国の言葉に似ているなと思うこともあるから、そういった楽しみ方ができるのであればドイツ語はパーフェクトな言語だと思うし、EUの中心の国でもあるから市長の演説なんかも何を言っているか自分の言葉で分かるともっと楽しくなると思う」

ドイツ情報のメルマガ
ONOMICHI - EHER WOHNEN ALS ÜBERNACHTEN - Teil II
Was ist eine lokale Spezialität in Onomichi, die häufig von den Einheimischen gegessen wird? Nudelsuppe habe ich schon gegessen. Deswegen dachte ich an Okonomiyaki.
Kurz erklärt, Okonomiyaki wird häufig als japanischer Pfannkuchen beschrieben, weil es rund ist, und weil es auch aus Mehl und Wasser gemacht wird. Trotzdem, Okonomiyaki ist kein Pfannkuchen, weil es aus mehr als Mehl und Wasser besteht: Kohl und Frühlingszwiebel, Fleisch und Meeresfrüchte gehören dazu. Was Onomichi’s Okonomiyaki anbelangt, man fügt normalerweise noch Muskeln des Hähnchens hinzu.
Takashi UEMURA
Lesen Sie Teil 1 hier.
Kunsttempel und Literaturgasse
Gegen 7 Uhr stand ich auf. Ich war im Bett, aber hatte kein Gedächtnis, wie und wann ich wohl ins Bett gekommen war. Angeblich war ich besoffen gewesen. Das war noch müde, weshalb ich wieder ins Bett ging.
Ich überlegte mir, welche Sehenswürdigkeiten ich in der Stadt besuchen wollte. Ich bin kein Typ, der alles im Voraus entscheidet. John Lennons „Imagine“ hat einem Verse, wo der Autor hofft, dass alle Leute im jetzt leben („Imagine all the people living for today“). Das hat keinen direkten Zusammenhang, aber ich entscheide mich erst am Morgen was ich mache, wenn ich auf einer Reise bin.
Da ich am vorherigen Tag am Meer gewesen war, wollte ich diesmal einen Berg hochlaufen. Im Norden der Stadt liegt eine kleine Bergkette, auf der der Senkôji-Tempel steht. Diese Information steht auch in meinem Reiseführer: Der Tempel bietet eine spirituelle Erfahrung und eine spektakuläre Landschaft. Dort gibt es eine Seilbahn, die von der Stadt bis zur Spitze des Berges fährt. Ich sprang aus dem Bett, putzte mir die Zähne, wusch mir das Gesicht und zog mich um. Nachdem ich meine kleine Tasche gepackt hatte, ging ich in den unteren Stock. Dort war schon der Besitzer, und er fragte mich über meinen heutigen Plan. Ich erzählte ihn von meinem Plan zum Wandern. Dann empfahl er mir, zu Fuß auf den Berg zu steigen. Es gibt nämlich noch etwas zu sehen: „Bungaku no Komichi“ - die Literaturgasse.
MATSUO Bashô, MASAOKA Shiki, SHIGA Naoya und HAYASHI Fumiko… Diese Namen sind sehr bekannte Namen in der japanischen Literatur, und sie hatten einen festen Zusammenhang mit der Stadt Onomichi. Deswegen hatte die Stadt eine Denkmalgasse gebaut. Das war die Literaturgasse. Der Besitzer erklärte mir über die Geschichte der Literatur, deren Inhalt ich im Voraus wissen musste, damit ich die Reise noch mehr genießen konnte. Ich war schon sehr neugierig über die kleine Gasse.
Und los. Ich bog rechts ab, lief ein Stück weiter, und befand mich in einer großen Einkaufsarkade. Es war erst um 9 Uhr, als ich dort war. Der Eingang der Literaturgasse war nichts besonders. Der Weg war ziemlich eng und steil, weshalb ich ein bisschen bedauerte, dass ich nicht die Seilbahn genommen hatte. Außerdem lief der Weg durch die Häuserallee, deswegen gab es nichts Spannendes zu sehen. Zumindest konnte das Geld für die Seilbahn sparen.
Trotzdem, plötzlich gab es da eine Entdeckung. Da war ein leerer Brunnen am Weg. Am Brunnen stand ein Schild, was über den Gebrauch des Brunnens lehrte. Plötzlich bekam ich eine Vorstellung davon, wie die Bewohner im Bergteil der Stadt zusammenlebten. Ich überlegte mir, dass sie sich jeden Tag z.B. am Vormittag am Brunnen gesammelt hatte, und sich über etwas Alltägliches unterhielten. Mit dieser Überlegung ließ mich ein bisschen vom Gefühl der abenteuerlichen Reise los, und freute mich stattdessen.
Nach ungefähr dreißig Minuten erreichte ich die Spitze des Berges und ich konnte einen schönen Blick aufs Meer werfen. Hinter mir lag der Senkôji-Tempel. Der war zwar einer von Onomichi’s Touristenmagneten, aber er war auch ein lokaler Tempel, wo die einheimischen Leute häufig zum Beten kamen. Ich bin kein begeisterter religiöser Mensch, sodass ich die Geschichte des Tempels nicht im Voraus gelernt hatte. Trotzdem fühlte ich mich in der besonderen Atmosphäre wohl. Es war mein Wunsch, dass ich mindestens eine Woche lang in Onomichi bleiben wollte, damit ich mehr über den Tempel und die Umgebung wissen konnte.
Nach dem Beten lief ich zurück in Richtung der Literaturgasse. Die Gasse war so eng, dass dort nur zwei Menschen nebeneinander stehen konnte. Plötzlich kam ich in eine Gasse hinein, in der sich Cafés sammelt. Ich erreichte die Literaturgasse.
Die Atmosphäre wurden für Besucher als eine Welt der japanischen Literatur beschrieben. Das Schlagwort in meinem Reiseführer lautet: Eine Zeitreise in die Meiji-Zeit. Trotzdem fand ich dies nicht so interessant, denn die Atmosphäre war nicht natürlich, und sie reflektierte nicht die authentische Seite vom Leben in Onomichi.
Ich war ein bisschen enttäuscht über das Literaturviertel. Dann sah ich eine Katze, die auf der Mauer eingeschlafen war. Plötzlich hörte ich jemand fotografieren, und erst dann habe ich gemerkt, dass es zahlreiche Katzen gab. Jede Katze fand ich sehr hübsch. Ich war ein bisschen hingerissen von den Katzen. Sie sahen aus, als ob sie wüssten, wie sie das Leben in der Gasse genießen konnten.
Die Katzen waren so niedlich, dass ich etwa eine halbe Stunde dort blieb. Ich war so in den Anblick der Katzen versunken, sodass die Zeit sehr schnell verging. Dann kam ich zur Erkenntnis, dass ich vermutlich ein komischer Tourist bin.
Mit dem Fotoapparat von meinem Smartphone konnte ich keine schönen Bilder von den Katzen machen, weil ich kein guter Fotograf bin. Trotzdem, die Existenz der Katzen selbst war für mich ein Symbol des Onomichi’s Lebens.
Zeig dich, was du bist, was du siehst und was du denkst.
Es gab bei den Katzen gibt es kein sollen oder müssen, was eigentlich für uns ein Bedürfnis oder Wunsch ist. Wir, Menschen, versuchten auch zu erkennen, was das Ich bedeutet, wobei es uns immer misslingt. Die Katzen in der Literaturgasse sind niemals philosophisch. Sie sollten mir sehr mutig erzählten, dass meine Philosophie total falsch ist.
Also, abgesehen von meinen Gedanken um die Philosophie, konnte ich wieder einen Teil des Wohnstils in Onomichi fühlen. Der Stil war viel lockerer als der in Kyoto. Erst nach dem beschäftigten Leben kann man bemerken, wie schön das lockere Leben manchmal ist. In Onomichi konnte ich viel Neues lernen.
Als ich wieder in der Stadt zurückkam, war es schon 17 Uhr. „Mahlzeit!“, dachte ich, weil ich schon Hunger hatte.
Okonomiyaki - Das Symbol der Menschenvielfältigkeit
Was ist eine lokale Spezialität in Onomichi, die häufig von den Einheimischen gegessen wird? Nudelsuppe habe ich schon gegessen. Deswegen dachte ich an Okonomiyaki.
Kurz erklärt, Okonomiyaki wird häufig als japanischer Pfannkuchen beschrieben, weil es rund ist, und weil es auch aus Mehl und Wasser gemacht wird. Trotzdem, Okonomiyaki ist kein Pfannkuchen, weil es aus mehr als Mehl und Wasser besteht: Kohl und Frühlingszwiebel, Fleisch und Meeresfrüchte gehören dazu. Was Onomichi’s Okonomiyaki anbelangt, man fügt normalerweise noch Muskeln des Hähnchens hinzu.
Ich war wieder an der Hafenstraße, weil es dort angeblich viele Okonomiyaki-Läden gibt. Um 17 Uhr öffneten die Läden noch nicht. Ich kam zu einem Laden, weil ich da einen Mann vor der Tür putzen gesehen hatte. Ihn fragte ich, ab wann der Laden auf war. Er sah mich streng an und sagte, dass er in fünf Minuten sein Geschäft öffnet. Ich ahnte, dass er sich noch erholen wollte. Das war ja Onomichi.
Fast genau fünf Minuten später war der kleine Laden auf. Dann kamen auch einige Leute, die angeblich Nachbarn waren. Alle sahen auch ein bisschen streng aus. Ich hatte die Sorge, dass ich im falschen Lokal gelandet war.
Plötzlich fängt der Ladenchef an, mich anzusprechen: „Woher kommst du denn? Was hast du hier vor?“. Ich antwortete auf seine Fragen und sagte ihm das ich aus Kyoto kam und nur zu Besuch in der Stadt war. Und waren alle ein bisschen verdutzt. Ich wusste nicht warum.
Dann sagte ein anderer Mann zu mir: „Haha, sei nicht so nervös, wir sind kein Yakuza. Wir sind alle gleich gute Menschen“. Er erklärt mir, dass Onomichi wegen eines Videospiels berühmt wurde („Ryû ga Gotoku 6). Er erzählte mir, dass es viele Fans gibt, die nach Onomichi kommen, um die im Spiel aufgetretenen Orte zu besuchen.
Danach unterhielten wir uns in lockerer Atmosphäre mit Okonomiyaki. Als ich über meinen morgigen Ausflug zur Ikuchi-Insel erzählte, dann bekam ich viele Tipps fürs Radfahren, Essen und Sehenswürdigkeiten. Auch haben wir über Baseball geredet: Alle sind große Fans von der Hiroshimas Baseballmannschaft. Zufällig hatten wir auch im Fernsehen des Restaurants ein Spiel gesehen. Ich hatte viel Spaß an diesem Abend.
Ja, das war Onomichi. Ich habe mehr zu erzählen, aber ich möchte die Leser nicht langweilen. Mein Fazit ist immer noch das Gleiche: Ich fand einen neuen Lebensstil während meiner Reise. Reisen ist nicht nur gut für Menschen, die eher Erlebnisse wichtig finden. Reisen, wie die Einheimischen: Das habe ich diesmal erfolgreich verwirklicht.
Fazit: Meine tolle Erfahrung außerhalb von den japanischen Touristenmagneten
Zum Schluss möchte ich die Reise nach Onomichi zusammenfassen: Jede Seite der Stadt zeigte mir das alltägliche Leben der Stadt. Natürlich fand ich das außerordentliche Livekonzert der gegenwärtigen Kunst sehr merkwürdig, aber es war eine Chance etwas über neue Künstler zu lernen. Die Landschaft und die Menschen dort halfen mir, sodass ich mir das Leben in der Stadt Onomichi vorzustellen konnte. Der Slogan der Stadt: Eher Wohnen, als Übernachten, passt sehr gut zu meinen Erfahrungen.
Dazu hätte ich zwei Fragen: